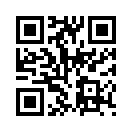› 沖縄の石、土、木、庭のブログ。 › 2月14日の記事
› 沖縄の石、土、木、庭のブログ。 › 2月14日の記事2024年02月14日
2月14日の記事

この日の朝は、菜園の畝立てのための枝が必要なので、まずはサルスベリの剪定作業です。

スッキリ。

畝立てに丁度良い量の枝が出ました。
山に入り、山のお世話をしつつ暮らしに必要なものをいただく里山暮らしは今の沖縄では難しいですが、庭の世話をしながら資源を循環させ、土に還すことはできます。
循環させることは傷んだ環境を回復させることへとつながっていきます。

さて、畝立てです。
畝を立てるところを幅60cm、深さ15~20cmくらい掘って、落葉と枝をたっぷり敷き込み、炭ともみ殻燻炭をばら撒いていきもの達の棲家作りです。

15~20cmくらい落葉、もみ殻燻炭を混ぜた土で畝を立て、軽く踏み固めます。
その上にまた落葉ともみ殻燻炭を敷き込み、さらにまた15~20cmくらい落葉、もみ殻燻炭を混ぜた土をかぶせます。
今回はそれをもう一回繰り返してできあがりとしました。

これを繰り返し5列の畝ができました。
微生物やミミズなどの小さないきもの達の棲家となった畝。
土はむき出しにせず落葉で覆うと良いのですが、これだけの面積を覆う落葉を集めるのは大変なので今回は草木チップで覆いました。(写真がなくてすみません)
これから、お施主さまが、野菜の種を蒔いたり、苗を植えたりされるにあたり、いろんな種類の野菜を植えていただく混植をおすすめさせていただいております。
単一野菜を〇〇cm間隔で整然と植え、化学肥料を施し、雑草はこまめに抜き、あるいは除草剤を用い、病害虫が発生すれば薬剤散布をし・・・という管理型(統治・制御型)の方法ではなく、
多種類の野菜を混植してもらい、雑草は抜くのではなく刈るようにし刈ったものはそのまま敷き込み土に還す。
すこやかな命の循環を考える。
それぞれの存在を尊重し、生存を脅かすことなく自由でいられるように。
化学肥料、除草剤、薬剤散布が私たち人間や自然にどのような影響を与えるのかを調べ、知らなければなりません。
小さないきもの達の生存を脅かし、小さないきもの達と植物との協力関係を壊し、それらの成分が土中に蓄積されたり川や海に流れ込んだりすることが多くの命に与える影響を考えていきましょう。
やれることはいろいろあります!
Posted by 艸木 at 09:34│Comments(0)