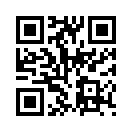2024年12月25日
12月25日の記事

ブログを更新する時間がなかなかとれずにおりました。
今年も、あっという間に過ぎていきました。
写真は工事前のものです。
クロキやソテツの撤去、サンダンカ等を植えたいという依頼でした。

クロトンが何年経ってもあまり成長しないというご相談だったり、
根腐れしている植物があったりという状況でした。

サンダンカはこちらのブロック塀に沿って植えることに。

砂利を取り除いてからの植栽となりますが、一筋縄ではいきませんでした。
話しは変わりますが、ここからが本題です。
建物を建てる時に、基礎工事や設備工事の後、土の埋戻しという工事があります。
今回は、その埋め戻す土が、環境にどのような影響を与えるのかということについてお伝えしていきます。
長くなりますので、結論から申し上げますと、
残土で埋め戻すと、環境を回復させるにはその土を掘り出して処理しないといけないので多くの手間とコストがかかりますよ。
だから埋戻しは自然環境を回復させるようなやり方で最初からやった方が手間もコストも自然環境的にも結果的にはいいですよ。ということです。
興味とお時間のある方はどうぞこのまま読み進めてくださいませ。

クロキを撤去するために敷石を外すと雨後でもないのに滞水していました。

池のような状態でした。
この時点では水道管からの漏水の可能性もゼロではないと思い慎重に周囲を掘り進めるも水道管は見当たらず。
かと言って、いっこうに水は捌けることがありませんでした。
兎にも角にも水を捌かさねばなりませんので、水を逃がせる所まで水みちを作らなければなりません。

いったん掘り出すと、地中に滞っていた水がどんどん集まりだしました。

根回しできるくらいまで水が捌けた時の写真です。

クロキを吊り上げると、根の中~下部は腐れておりました。
黒くなっているのが根腐れしている部分です。
このサイズのクロキだと根鉢の大きさは(高さ)50cmくらいですが、
上部20~25cmだけでしか生息できない地中の状況だったのです。
地中からはもちろん悪臭がします。
こうなると、深く根を張ることはできません。
深く根を張ることができるということは、環境を安定させることへとつながります。
酸素が不足し、有機ガス(メタンガスなど)が出たりすると、酸素を必要とするいきもの達は棲みにくくなり数が減っていきます。
そうすると、植物も弱っていきます。
なので地中の適度な通気通水というのはとても大事なのです。
適度な通気通水は植物と協力関係を結べる菌やミミズなどの小さないきもの達も棲みやすい環境となります。
それは、生物多様性へとつながります。
多種多様、いろんないきもの達が元気でつながり合い命をまっとうしているってなんかいいよね。
しかし、地中の通気通水を滞らせるような埋戻しをしたり、コンクリートで塞いだりしてしまうと、酸素を必要とするいきもの達は息苦しくなり呼吸ができなくなって減少したり死滅してしまったりします。

たまった水はまったく引いていくことはありません。
こちらの敷地で埋め戻しに使われていた土はいったいどのようなものかと言いますと、
沖縄南部特有の粘土質のクチャとクラッシャランと呼ばれる琉球石灰岩を砕いた砂利と石粉の混ざったものとコンクリート再生材、主にこの3種類をごちゃ混ぜにした土で、それをしっかりと転圧しているものですから、水が捌けず滞水状態となっているわけです。

擁壁のこの排水口が水の逃げ道となりますが、上記のような土なのでまったくゼロというわけではないでしょうけれども、排水口からはほとんど水が出ることはありません。
ひと昔前だと、こうした排水口がある場合、グリ石で水が抜けるようにするのは当たり前のことでしたが、近年ではグリ石を入れない現場とよく出会うようになりました。

途中、雨が降り水量が増えていますが、これまではこの水が通り道をふさがれ長らく地中に滞っていたのです。
こちらのお宅では2mほどの擁壁で囲まれた敷地の全部が上記のような埋戻し土となっていました。
結果、どこを掘っても土から悪臭がする状態で、植物は浅根となっています。
敷地のすべてを通気通水改良させるのがベストですが、それをするとたいへんな工事金額がかかってしまいます。
お施主様と相談し、今回は、新たな植栽に関わるところと最低限の水みちを作ることを改善していくことになりました。

土が黒っぽくなっているのは、土が酸欠状態となっているためです。(グライ化)
ここから悪臭が放たれますが、2~3日、空気にさらすと悪臭は消えました。

ここは地中の水みちをもう一カ所増やすためにクロトン側の花園の捨てコンを取り除き排水口へ。

こんな感じで排水口までつながっています。

最小限の地中の水みちを掘り終え炭を敷いているところです。

暗渠管は使用せず、掘ったところからはたくさんのコンクリート殻や石、瓦辺などが出てきましたのでそれらを利用することにしました。

植栽する場所は敷地の水みち確保を兼ねてグリ石を入れてます。
地中の通気通水が滞るような埋戻しをしてしまい、それを回復させようとした場合、
埋設物を破損させないよう、気を付けて掘っていかないとなりませんし、
また、掘った土がちょっとした手間で再利用できればいいのですが、
今回のような土だと捨てた方が時間的にもコスト的に良いとなったりして、たいへんな手間とコストが必要となります。
また、何でこのような土で埋め戻しがされてしまうのかというと、最大の理由はもちろんコストにあるわけです。
各建設業者さんはお施主様の負担を軽減しながら利益を上げていかないといけませんので、いかにしてコストダウンを図るかという切実な事情を抱えています。
ですから、残土と呼ばれるこのような土で埋め戻しをすることでコストダウンを図ることになってしまいます。
また、それが環境へ悪影響を与えることを業者さんもお施主さんも知らない場合、安くできるんだからそれでいいとなってしまうのが今現在あちこちで行われていることです。
そうしたことが、高度成長期以降、急速に拡大し、山や川や海が傷つけられ、いきもの達は減少し、自然は衰弱し・・・、気候変動や洪水、土砂崩れなどの災害はは自然的なものなのか人の行為によるものなのか・・・、いろんなことが目の前の現実としてあらわれてきています。
多くの方々が、それぞれの立場で自然環境を良くしていこうと様々な活動がなされています。
私の目の前にあるもののひとつとして、自然の回復を促すためにも地中の通気通水を考慮せずに残土で埋め戻しをするのはやめましょうということを多くの人に知ってもらい、地中の適度な通気通水が確保されるような埋戻しをしていこうということがあるわけです。

工事期間の2/3は見えない地中のことに手をかけ、残り1/3は石の据え直しや植栽などの目に見える仕事です。
植栽はサルスベリ等もともと鉢植えをたくさんお持ちでいらしたのでそれらを地植えし、新たな植栽はクチナシやタマリュウ、ヤブラン、ツワブキくらいでしょうか。
首里にあるこちらのお宅はもともと造り酒屋をされていたということでした。
3っつの井戸があり、フール(トイレ兼豚小屋)もあったことから、当時使用していたなごりの石がたくさんあるのです。
酒屋をされていた当時は水もきれいだったことでしょう。
今では、環境を衰弱させないと建物が建てられないような規則になっていますので、地中の通気通水を遮断し、土は腐敗し、水は汚され・・・ということが人間が構造物を造るいたるところで行われているのです。
お施主様とそうした会話を通し、「我が家の事例を発信することで現状を多くの方に知ってもらいたい!」というお言葉をいただきました。
私たちが暮らすことで、自然の一員として自然の豊かさや多様な生態系を保ち続けられるような社会にしていきたいものです。
そのための一歩として、埋め戻しをどうするかということを、改めて考えていくきっかけとなれば幸いです。

フールに使われていた石です。

土留めと腰掛をかねた長石。

飛石は石臼で。

ニービ石もありました。

土留めやら維持管理のための飛石を打ったら意図せず笑顔のようになりました。
かなり長いブログになってしまいましたので、サンダンカの植栽についてはまたの機会にアップします。
長々とお読みいただきどうもありがとうございました。
Posted by 艸木 at
11:42
│Comments(0)
2024年10月18日
10月18日の記事
11月17日 南城市役所の裏の森でイベントが開催されます!
私も、「地球のおていれ」ということで関わらせていただくことになりました。
なんじょう祭に興味のある人はイベントに加われますよとお知らせがあり、打合せにお伺いしたところ、あれよあれよという間に、参加決定となり今日にいたります。
一応、この辺までできるといいよねという目標はありますが、どこまでできるかはやってみてです。
ゆるい感じで楽しみながら、穴や溝を掘ったり、そこに枝や落葉を仕込んだり・・・、土地が呼吸を取り戻せるように傷んだ環境のお手入れをしていきます!
ご興味のある方はチラッとでかまいませんのでお立ち寄り下さい。
汚れてもよい服装、軍手があると良いかと思います。
他にも楽しいイベントが盛りだくさんとなっていますので、たくさんの方々のお越しをお待ちしておりまーす!
Posted by 艸木 at
07:56
│Comments(0)
2024年09月08日
9月8日の記事

那覇市の住宅地で庭のお手入れをしてきました。
長いこと手つかずで、お客さまも自ら頑張ってお手入れをしようと試みるも「大変すぎてどうしてよいのかわからない。」というご相談でした。
枝葉をかき分けないと進めない状況でしたが、手つかずだったことが幸いして微生物や植物を含めた庭の状況としては概ね良好でした。
直射日光が地面を照り付けるような剪定をしてしまうと、微生物も減り、そのことで植物の元気も低下していくと考えているので、庭が樹冠で覆われている状態を維持しつつ、人が歩きやすいようにすると同時に、適度な風通しを催して、土の中のいきもの達や植物が呼吸をしやすいようにして庭の健康を維持していくことをお話しすると、お客さまも喜んでくださり仕事をさせていただくことになりました。
余談ですが、直射日光が地面を照り付けるような剪定をして土をむき出しにすると砂漠化を防止するかのようにすぐに雑草が生えてきます。土のコンディションが悪いとイネ科の強い雑草が生えてきたりするので、雑草はその土地の状況を知らせてくれる大事な存在です。

作業後の写真です。
落葉はそのままにします。
山の中の香りがする庭です。
作業中もたくさんの種類の鳥が庭にやってきました。

作業後、お客さまに質問をされたことを書いておきます。
Q 落葉はきれいに掃除した方がいいですか?
A 掃除して土をむき出しにすると、微生物が減り、植物も弱りますので落ち葉が地面を適度に覆っている状態を維持することで庭の健康を保っていきましょう。
Q 起伏の多い庭なので歩きやすくするために、たいらにしてもいいですか?
A 起伏があることで地上地下ともに空気と水の動きが出ます。いわば大地が呼吸しやすい状況となりますので平らにはしないで起伏を大事にしましょう。
多くの方々が落葉をきれいに掃除して土をむき出しにして、歩きやすさを優先するあまり起伏をなくして平らにしてしまいます。
これらは土の中のいきもの達や植物、自然、大地の呼吸にとっては痛めつけられることとなります。
人も、いきもの達も、自然もみんながよかったねと言い合える庭をつくっていきましょう!

お客さまが、オオゴマダラが大好きなのでホウライカガミを植えたいとおっしゃっていました。
この庭にピッタリだなぁと思い嬉しくなりました。
庭って持ち主の好みが出ます。
トロピカルな雰囲気がお好きな方は樹木の合間に観葉植物を植えたり、ヤシを増やしたりしても楽しいでしょうし、
楚々とした雰囲気にしたいなら、ナガミボチョウジやノシランなど日陰でも花を咲かせたり、実をつけてくれるような植物を植えるのもよいかと思います。
コンクリートに囲まれた住宅地の中に、山の香りがする庭が残っていて嬉しくなりました。
こういう庭や緑地、どんどん増やしていくぞー!えいえいおー!
Posted by 艸木 at
10:55
│Comments(0)
2024年09月04日
9月4日の記事

北谷は国大道路沿いにある「和さびや」さんの工事が完成です。
艸木では石仕事をさせていただいきました。
昨日、お祝いに観葉植物をお届けした際に写真を撮ってきたのでご紹介です!
2トンもある本部石灰岩の台座は大好評!
花瓶を飾るとより良い雰囲気に!

入口は御影石と白玉石に、本部石灰岩です。

観葉植物はモンステラとブラッサイア。

個室!


お手洗いへの伝い!

グリーンアラレア!

沓脱石!

和さびやさんの外観です!
オープン日はまだわかりませんが、もう間もなくと思います。
店舗の仕事はたくさの業者さんと賑やかにやらせてもらい楽しかったです。
店舗設計は株式会社NO-SCALEさんでした!
Posted by 艸木 at
13:16
│Comments(0)
2024年08月16日
8月16日の記事

坪庭、仕上がりました!
水がなかなかはけず、滞水しがちな場所でしたが、スカッと改善です!
やがて植物の根が坪庭を張り巡り、水と空気の通り道がさらにしっかりとしてくるでしょう。
大地の通気孔がひとつ増えました。
機会をくださったお施主様に感謝です。
この調子で大地の呼吸をどんどん取り戻していきますよ!
Posted by 艸木 at
10:14
│Comments(0)
2024年08月12日
8月12日の記事

坪庭の土は締め固まっていたので、まずは通気通水の改良です。
まずは、根切棒で砕きながら土の取り出し作業。(スコップがなかなか入らないくらい固い土でした)
柔らかな土が出てくるところまで掘っていきます。
この層まで掘ると土からじんわりと空気が抜けていく気配が感じられる。
土地が呼吸をしはじめた気配。よっしゃ!って気持ちになります!

水はけが悪く、土が泥になってしまっている部分も手当をしていきます。

泥化していたところは、泥の上に落葉と炭を撒いて、移植ゴテで撹拌し、保護膜とします。
保護膜はかさぶたみたいなイメージです。
泥化して傷口となったところに落葉と炭でかさぶたをつくって回復を促すといったところでしょうか。

その後、縦穴をあけ、溝を掘るなどしてから落葉と炭を撒くことで通気通水改良の下地が完了です。
これから、地中の空気の動きが滞らないように植栽へと続いていきます。
Posted by 艸木 at
07:16
│Comments(0)
2024年08月11日
8月11日の記事

敷石と石積みの同時進行です。

石積みの裏側に枝葉を入れ込んで植物の根が元気に育ってくれる環境にします。
枝葉の入れ方は石積みの高さなどによって工夫をしながらです。
敷石も石積みも土地の呼吸を確保しながら進めていきます。
土地の呼吸とは、土の中の通気通水を塞ぐことなく促すこと、土の中の通気通水が適度であるということ。
大地は呼吸をしているということをみんなで共通の認識としていければ人と自然のかかわり方がガラッと変わります。

枝と落葉を仕込んだところにはびっしりと根が!(枝や落葉がない土だけのところでは短期間でこうはなりません。)
根は大地の呼吸を保ってくれている大事なお方なのです。
微生物、ミミズ、落葉、枝葉、イノシシ・・・いきものたちは生きることを通してみんなで大地の呼吸を確保しています。
地球のお世話になりながら、地球のお世話をしている。
人も自然と共に生きることを暮らしの中に取り入れていければ、楽しいだろうなぁと思うのです。
Posted by 艸木 at
07:06
│Comments(0)
2024年07月18日
7月18日の記事
造園屋なので、庭や自然が好きなお客さまとお会いする機会が多いです。
庭の相談を聞いたり、お話を進めていくなかで
最近「あれれ?」と思ったのですが
「自然を大事にしたいよね」
「美しい自然を守りたいよね」
などという話しが出ることも多々あるのですが、
皆さん美しい自然とは具体的にどういう状態なのか
自然を大事にするとはどういうことなのか、
自然を守るとは自然にダメージを与えないようにするということでもあるのですが、
何をすると自然にダメージを与えてしまうのか、
そういうことについての認識や情報の共有がまったくできていないのです。
なので、お庭の相談にお伺いした際、せっかく来たのでということでデモンストレーションをしながら自然の仕組みとか、ダメージの回復方法とかをお客さまのお庭の状況に合わせていろいろとお話ししてくるのですが、お客さまも目から鱗だったり、確かにそうだよね!と喜んでくださり、これが実に楽しい!
何気なくやっていたことが実は自然にダメージを与えていたりとかするのですが、一度知ってしまえば庭や自然との関わり方も変わってきます!
自然の仕組みや自然にダメージを与えてしまう事柄、傷んだ自然の回復方法とか、多くの皆さんと認識を共有していくことが今とても大事なことだと思っています。この内容が共有できていないことも、自然破壊に歯止めがきかない大きな一因であるのではないかと思うからです。
そういうわけで、お庭でのデモンストレーションを自然の仕組みなどの情報共有をかねたお打ち合わせをどんどん募集します!
お庭のことで何かお困りの方、新築にともなう庭づくり、庭のリフォームなど、
ご希望の方は遠慮なくお問い合わせください。もちろん相談は無料ですよ!
みんなで力を合わせて、傷んだ自然を回復させたり、たくさん木を植えて緑豊かな庭や緑地をたくさんつくって地球を楽園にしていきましょう!

朝食後、庭に出るとアオミオカタニシも朝ごはんを食べてました。
もぐもぐ食べてる姿にほっこり。
環境を整えればいきもの達も戻ってきてくれます。
自然破壊がドンドン進んでしまいますし、ヒートアイランド現象なんてのもあってなのか今年は特に暑いです。
私たち人が、自然に守ってもらえるような暮らしぶりができるようになることが大事なことと思っております。
庭の相談を聞いたり、お話を進めていくなかで
最近「あれれ?」と思ったのですが
「自然を大事にしたいよね」
「美しい自然を守りたいよね」
などという話しが出ることも多々あるのですが、
皆さん美しい自然とは具体的にどういう状態なのか
自然を大事にするとはどういうことなのか、
自然を守るとは自然にダメージを与えないようにするということでもあるのですが、
何をすると自然にダメージを与えてしまうのか、
そういうことについての認識や情報の共有がまったくできていないのです。
なので、お庭の相談にお伺いした際、せっかく来たのでということでデモンストレーションをしながら自然の仕組みとか、ダメージの回復方法とかをお客さまのお庭の状況に合わせていろいろとお話ししてくるのですが、お客さまも目から鱗だったり、確かにそうだよね!と喜んでくださり、これが実に楽しい!
何気なくやっていたことが実は自然にダメージを与えていたりとかするのですが、一度知ってしまえば庭や自然との関わり方も変わってきます!
自然の仕組みや自然にダメージを与えてしまう事柄、傷んだ自然の回復方法とか、多くの皆さんと認識を共有していくことが今とても大事なことだと思っています。この内容が共有できていないことも、自然破壊に歯止めがきかない大きな一因であるのではないかと思うからです。
そういうわけで、お庭でのデモンストレーションを自然の仕組みなどの情報共有をかねたお打ち合わせをどんどん募集します!
お庭のことで何かお困りの方、新築にともなう庭づくり、庭のリフォームなど、
ご希望の方は遠慮なくお問い合わせください。もちろん相談は無料ですよ!
みんなで力を合わせて、傷んだ自然を回復させたり、たくさん木を植えて緑豊かな庭や緑地をたくさんつくって地球を楽園にしていきましょう!

朝食後、庭に出るとアオミオカタニシも朝ごはんを食べてました。
もぐもぐ食べてる姿にほっこり。
環境を整えればいきもの達も戻ってきてくれます。
自然破壊がドンドン進んでしまいますし、ヒートアイランド現象なんてのもあってなのか今年は特に暑いです。
私たち人が、自然に守ってもらえるような暮らしぶりができるようになることが大事なことと思っております。
Posted by 艸木 at
19:20
│Comments(2)
2024年05月31日
5月31日の記事
ハウスメーカーさんへ行ってきました。
商談ルームからはイジュの森の大パノラマ。
他にも、ヒカゲヘゴ、タブノキ、ナカハラクロキ、ホルトノキ、ハゼノキ、ヤブニッケイなどが自生している場所です。
谷間に流れる小川が、この森を支えてくれています。
以前、イジュの森を大事に守りながら本社ビルを建設したいというお話しから、手入れをさせていただいた森です。


上の2枚は手入れ直後の当時の写真です。
当時、森は乾燥し、木々は弱り(枯れ木や枯れてしまいそうな木々もたくさんありましたので写真はそうした木で土留めをしたものです)、川の水もあまりきれいではなく、藪化が進み傷んで大変な状況でした。
今も勉強中ですが、その頃は自然の仕組みついての理解が今よりもなかったので、写真を見るともっとこうしておけばよかったなぁということがたくさんありますが、それでもここまで見事に回復したのはやはりこの森が元々持っているポテンシャルが高いということ、そして、ハウスメーカーの社長さんや工事関係者さんが極力木を伐採せず、枝を切らずということで森を大事にして工事を進めてくれたということが大きな理由だろうと思います。(工事中、1本だけはやむを得ず伐採したそうですが)
先日、お伺いした際、森には藪がなく、しっとりとコケも載りはじめ、見違えるほどになっていました。
こういう場を見ると励みになります。
地中の通気通水を促す水脈を回復させ、微生物や小さないきもの達が棲みやすい環境となり、木々も元気になっていく。
自然が元気ならば、多くのいきもの達も人間も元気でいられます。
人と自然が元気で共存していける場所をひとつでも多く残し、ダメージを受けているところは自然にお力添えをいただきながら回復させ、健やかできれいな自然をたくさん未来につないでいきたいと改めて強く思いました。
Posted by 艸木 at
18:28
│Comments(0)
2024年05月21日
5月21日の記事

土の中の空気と水の流れが停滞し、居心地のあまり良くない感じがする庭でしたが、溝を掘り、点穴(縦穴)をあけ、落葉や小枝、炭、燻炭を施し、庭が呼吸できるようにしたところ、みるみると庭の空気感が変わりました。以前はズーンと重たい感じがしていたのですが、今は、すっかり軽くなりました。
土の中の嫌な空気が抜け、新鮮な空気が土の中に入っていくことができるようになったからなのだと思います。
新鮮な空気が入り、古い空気が抜けるのは大地の呼吸。
空気と共に、水も循環します。
酸素などが溶け込んだフレッシュな水は、好気性菌が増え、土が腐敗へと向かうのを防いでくれます。
それは木々の健康には欠かせないこと。
暗く、ただ佇むことしかできないように見えたカイヅカイブキも元気を取り戻してくれて嬉しいかぎりです。


これは庭が呼吸できるように改善した直後の重たい空気感が充満していた頃の写真です。
沖縄は今日、梅雨入りです。
水が溜まりやすい、水はけが悪い、雨で土が流出してしまうなど、雨のおかげで人が手を入れてあげなくてはならない場所(言い換えると庭が不健康な場所)がわかりやすくなりますので、お庭の健康状態をチェックするにはいい時期といえるのではないかと思います。
Posted by 艸木 at
16:11
│Comments(0)
2024年05月13日
5月13日の記事

庭の改修が完了しました。
琉球石灰岩の敷石通路の下も水と空気が通るように造作をしています。
据えた石の下も、もちろん通気を確保。
植栽はお施主さまが選んでくださったインディア、オキナワシャリンバイ、アガパンサス、ヒメアラマンダ、シラン、ツワブキ、ヤブランです。

改修前です。

芝生を剥がしおえたところです。
カイヅカイブキとゲッキツの根張りが擁壁側に集中しており、他へは排水桝へ向かうところ以外は殆ど根が張っていませんんでした。
庭全体での水と空気の浸透がいまいちな場合、壁と土がくっついているところは水と空気が入りやすいので、そちら側に根が向かうのはよくあることでして、こういう根の張り方を見るとここは水の浸透が不良な庭という判断の目安のひとつとしています。
排水桝をめがけ地表を這うように根を張らしていたのは、雨水が排水桝をめがけて地表を流れる際に空気も一緒に動くので地表の浅いところだけ根を這わせたのでしょう。

床掘を終えたところで大雨。
1日経過しても水が浸透する気配はないです。
こういう土中の環境だと、樹木も健康にということにはなかなかなりません。
放っておくと、オオバギ、ギンネム、クワノキといった木々が土中に空気や水を浸透させようとして生えてくるということになります。

庭全体に空気と水が流れるように造作をほどこしました。


庭全体が雨水濾過の場となるように、落葉、小枝、炭、もみ殻燻炭をたっぷりといれます。
こうすることで、樹木の根が庭全体に張り巡り、微生物との共生もできるような環境になればと思っています。

住宅地の庭の土の中は、多かれ少なかれその本来の機能(大地としての機能)を全うできないという問題を抱えています。
雨水を濾過し、涵養された水の循環を促してくれる大地の営みを、各家庭の庭から再生させていくことは、庭を持つ方々ならばすぐにできることです。
沖縄にかぎらず、各地で自然が傷つけられ、破壊され続けています。
傷んだ自然を再生させていくこと、地球にやさしい開発を模索していくことが大切だと思います。

シラン。

アガパンサス。
おだやかな表情の庭になったのではないかと思います。

おまけのプチ菜園。
樹木の根を傷めないように、シマトネリコの幹を菜園の囲いにしました。
落葉、炭、燻炭をたっぷりと敷いているのでやがて菌糸ものってくることでしょう。
Posted by 艸木 at
17:53
│Comments(0)
2024年04月22日
4月22日の記事

芝生を撤去して庭の作りかえです!

芝生を剥ぎ取ると、写真だとわかりにくいのですが、カイヅカイブキとゲッキツの根が地中の水と空気の動きがあるところを目指して偏った這い方をしているのがわかります。
そして、ちょっと掘ってみると浅根であることも見て取れました。
地下の深いところでの水と空気の動きが鈍いので、根が深くまで行きたがらないのだと思います。

石を敷き込み通路をつくるため、少し深めに掘り下げたところで、その日の夜からものすごい雷雨。
翌日も結局お昼頃まで結構な雨が降りましたので、作業再開は翌々日からとなりました。
庭を掘り下げたところに、この雨はとてもラッキー!
水の浸透がどの程度のものかがはっきりしますので!
作業再開となりますが、水がスーッと浸透していく気配はまるでなく、見ててもわからないくらいじんわりじんわりと超スローペースで浸透している感じ。
これがわかると、どの程度まで何をしたら良いのかが明確になります。

3m弱の擁壁に囲われた庭です。
排水用の穴は開いていますが、上段の穴からはまったく水が出ておらず、下段の穴からじんわりにじみ出ております。
庭の天端から上段の排水口までの高さは130cm。
そこが土が目詰まりして、滞水させているゾーンとなります。

この庭の呼吸と元気を回復させるにはいくつか方法がありますが、
まずはカイヅカイブキとゲッキツのダメージを最小限にすること。
そして予算面でもあまり負担が大きくならないこと。
この二つを考慮して、今回はこんな感じでやってみることにしました。
2カ所の縦穴は排水口まで掘り下げ、
他に9カ所50~70cmの深さの縦穴を掘り通気口としました。
そして、各縦穴を水と空気の動きが出るように高低差をつけながら溝でつないでいます。
そして、溝が後々目詰まりしないように竹筒を入れました。
水と空気の動きがあるところはフレッシュなので、そこは根にとっても居心地がよく、そこを目がけて根を伸ばします。
愛しい子を抱きしめるように、庭全体を根が大切に抱きしめてくれるよう下地の造作をしました。
根が抱きしめるのは土だけではありません。
微生物、ミミズなどの小さな生きもの達の棲み処となりながら、彼らもまるごと抱きしめてくれるのです。
木ってすごいなぁって思います。

さらに、小枝、落葉、炭、燻炭を溝の隙間に入れ込みます。



次に全体的に、落葉、炭、燻炭を敷き込みます。

そして、土をかけて下地のできあがりです。
これは地中での水と空気の動きをよくするだけではなく、庭がちょっとした水の濾過装置としての役割を持てるようにと思い施したものです。

ここは、先日、偶然見つけた海岸です。

とてもきれいな海岸で、海の底のいたるところから水が湧きだしていまいた。
きっと陸地から地中の水脈を通って湧き出ている水でしょう。
きれいにろ過され、命を養ってくれる水です。
あらゆる場所で開発はどんどん進み、こういう場所はずいぶんと少なくなっていることと思います。
水を地中に浸透させることなく、表面排水としてろ過もせず海まで流してしまっては、生態系はますます危うくなり自然は傷んでいきます。
傷んだ自然を回復させ、大地の呼吸を取り戻そうではありませんか。
きれいな自然はきれいなまま後世につなぎ、私たちが汚してしまったところは少しでもきれいにしていきたいものです。
今、私たちにできることはたくさんあります。


太陽が沈む直前まで、ゆっくりすごしました。
美しい自然がありがたく・・・。
Posted by 艸木 at
18:47
│Comments(0)
2024年04月11日
4月11日の記事

イヌマキです。

毎年、キオビエダシャクが大量発生するこの時期に薬剤散布と合わせて剪定をされてきたようです。

裏手にはカイヅカイブキ。
庭は、建物とブロックの基礎で囲われており、水の逃げ道はなく、
土は固く締まり、湿気がたまっている感じでした。
木も元気がありません。
カイヅカイブキは、支柱がなければ強風で簡単に倒されてしまうくらい根元はグラついていました。
農薬散布と剪定の依頼でしたが、
農薬を散布すると、木と協力関係にある他の生きもの達にも影響を及ぼし、ますます木を弱らせてしまう。
木が弱れば、その木を枯らし土に還そうと自然は作用するので、またキオビエダシャクなどの木を弱らせる虫などが大量に発生する。
それでまた、農薬を散布し、ますます木が弱る・・・という悪循環です。
ここは人が痛めてしまった庭ですから、人の手で再生できるきっかけを作ってあげなくては・・・、
農薬を散布するのではなく、庭が元気を取り戻せるよう、処置をするのが先決なのでは、というようなお話をさせていただきました。
そして、今回はこれまで散布し続けた農薬を使うのをやめ、まずは庭の元気を取り戻そうということになりました。
水は浸透するものの、土の中の空気が動かず、湿気がこもるこちらの庭。
カイヅカイブキがある方は、あちこち土を掘りますが、根がほとんどありません。
イヌマキ側は、建物基礎の下に潜り込んだ根が数本と、元気なさげな根が地表10~15cmの浅いところにわずかにあるという感じでした。
基礎の下に根が潜り込んだのはそこの方がまだ空気と水の動きが庭よりもあるからということだと思います。
30年以上、毎年農薬を散布され続けた土の中はミミズなどの虫もおらず、命の気配がありませんでした。





根がたくさん出てこれるように、溝、大きな縦穴、小さな縦穴には竹、枝葉、炭、くん炭、落葉を入れて土の中の空気と水に流れをつけるのと、微生物や菌糸の棲み処づくりです。
グランドカバーは全面に炭、くん炭、落葉をまいて今回は終了。
イヌマキの剪定はまだ時期が少し早い感じでしたので、改めてということになりました。

毎日顔をのぞかせてくれたオキナワキノボリトカゲです。
Posted by 艸木 at
18:23
│Comments(0)
2024年03月25日
3月25日の記事

虹亀商店さんです。

風が通らず、水が溜まりがちでジメジメしている場所です。
建物が傷みやすくなってしまうので環境を改良することになりました。

写真ではわかりませんが、山の中は獣道のような感じで風が通るように植物をととのえています。
建物の際の滞水しがちな場所は溝を掘ることで改善。
作業後、心地よい風が入ってくるようになりました。
これは建物を長持ちさせたり、床下などのカビを防止し健康に配慮したりということになるかと思います。
隣山の自然と古民家、そしてそこで暮らす人が良好な関係を保つことができます。

風を通し、水を地下に浸透させながら流していきます。

溝堀で出た土は菜園の畝として生まれ変わります。
写真は作業途中のもので、山をととのえた時にあった朽木を少し頂戴して畝の中に入れているところです。
Posted by 艸木 at
07:57
│Comments(0)
2024年03月12日
3月12日の記事

モンパノキです。
海岸沿いなどでよく見かけます。
美しい木だなぁと見入ってしまう。

本部石灰岩を据え、モンパノキとスパイダーリリーを植えました。

石を据え、植栽をしたところは土の中で微生物やミミズなどの小さな生きもの達が過ごしやすいようにしています。

こちらの庭は芝生だけの庭でした。
庭の改修ということで最初はコンシンネとベンジャミンを植え、
次にオブジェの設置、
それからテーブルセット、
そして今回の本部石灰岩、モンパノキとスパイダーリリー。
木を植えるなどしていくと奥行が出てきます!
なにより庭が楽し気になっていい感じです!

オブジェの周りにはシロツメクサ!

Posted by 艸木 at
08:32
│Comments(0)
2024年03月04日
3月4日の記事

クワズイモを植えました!
沖縄の植物は魅力いっぱいです!


アオミオカタニシ!
近所の山ではクワズイモの葉にいるのをたまに見かけします。
準絶滅危惧種として環境省のレッドデータに記載され、
森林開発により生息地が減少し、個体数も減ってしまったようです。
お庭をお持ちの皆さま、もしよろしければ、沖縄に自生している地元の植物をほんの少しでかまいませんのでお庭に植えてみませんか?

Posted by 艸木 at
12:03
│Comments(0)
2024年02月24日
2月24日の記事

剪定したシマトネリコの枝を杭にして・・・、

打ち込んだ杭に枝を編み込んでシガラミのできあがり!
剪定したシマトネリコの葉で土を覆いますので、葉っぱが散らばらないようにするための囲いです。

シガラミで通路を縁取りするだけで歩くのが楽しくなります!
小さな生きもの達の棲家にもなり、植物も元気に!
庭が多様な生態系を保持するようになり、豊かさを取り戻していきます。

「シマトネリコは成長が早く、手入れが大変」という声を聞くことが多いですが
剪定した枝で何か作ったり、葉っぱを土に覆うことで雑草を抑制した上に、庭の土が豊かになる楽しみがわかると、剪定が待ち遠しくなります!
タブノキ、ヤブニッケイ、クワズイモなどが植えられた沖縄でよく見られる植生の雑木の庭と思いきや、アロカシアとかの観葉植物やブロッコリー、ニラ、ナスなどの野菜もしれっと植えている何でもありの「ちゃんぷるーガーデン」です。

Posted by 艸木 at
08:46
│Comments(0)
2024年02月21日
2月21日の記事

クスノキで制作したオブジェを設置してきました!

オブジェの下は砂利を敷き、水が地中深くまで浸透するように細工を施しております。
木で制作したオブジェですから、もちろん朽ちていきます。
その過程でキノコが生えてきたりもするかもしれません。
オブジェがボロボロと朽ち剝がれてきたら、菜園や植込みスペースで土に還してもらうこととなります。
そこでは糸状菌なども生じることでしょう。
命が循環する庭です。
Posted by 艸木 at
13:02
│Comments(0)
2024年02月18日
2月18日の記事

崩積みと丸太による土留めが仕上がりました。
菜園を囲うのはコバノサンダンカ。
他に、オキナワシャリンバイやトベラ、アガベアテナータを。
石の隙間にはイシギク、ヤブラン、ムラサキオモト、アスパラスプレンゲリー、オリヅルラン、カンゾウを植えました。


海が近いのでイシギクをたくさん植えています。
自生しているかのようにうまいこと馴染んでもらえれば嬉しいですね!


土の中の空気が動き、水が浸透し、崩積みによる石とすき込んだ落葉や枝葉を棲家として植物、微生物、虫、ミミズなどの小さないきもの達が共存することで安定した環境となり、たっぷりと養分を含んだ水が海へとつながり・・・、この庭がすこやかな生態系を支えていく循環のひとつのポイントとなれば嬉しいかぎりです。
Posted by 艸木 at
10:04
│Comments(0)
2024年02月14日
2月14日の記事

この日の朝は、菜園の畝立てのための枝が必要なので、まずはサルスベリの剪定作業です。

スッキリ。

畝立てに丁度良い量の枝が出ました。
山に入り、山のお世話をしつつ暮らしに必要なものをいただく里山暮らしは今の沖縄では難しいですが、庭の世話をしながら資源を循環させ、土に還すことはできます。
循環させることは傷んだ環境を回復させることへとつながっていきます。

さて、畝立てです。
畝を立てるところを幅60cm、深さ15~20cmくらい掘って、落葉と枝をたっぷり敷き込み、炭ともみ殻燻炭をばら撒いていきもの達の棲家作りです。

15~20cmくらい落葉、もみ殻燻炭を混ぜた土で畝を立て、軽く踏み固めます。
その上にまた落葉ともみ殻燻炭を敷き込み、さらにまた15~20cmくらい落葉、もみ殻燻炭を混ぜた土をかぶせます。
今回はそれをもう一回繰り返してできあがりとしました。

これを繰り返し5列の畝ができました。
微生物やミミズなどの小さないきもの達の棲家となった畝。
土はむき出しにせず落葉で覆うと良いのですが、これだけの面積を覆う落葉を集めるのは大変なので今回は草木チップで覆いました。(写真がなくてすみません)
これから、お施主さまが、野菜の種を蒔いたり、苗を植えたりされるにあたり、いろんな種類の野菜を植えていただく混植をおすすめさせていただいております。
単一野菜を〇〇cm間隔で整然と植え、化学肥料を施し、雑草はこまめに抜き、あるいは除草剤を用い、病害虫が発生すれば薬剤散布をし・・・という管理型(統治・制御型)の方法ではなく、
多種類の野菜を混植してもらい、雑草は抜くのではなく刈るようにし刈ったものはそのまま敷き込み土に還す。
すこやかな命の循環を考える。
それぞれの存在を尊重し、生存を脅かすことなく自由でいられるように。
化学肥料、除草剤、薬剤散布が私たち人間や自然にどのような影響を与えるのかを調べ、知らなければなりません。
小さないきもの達の生存を脅かし、小さないきもの達と植物との協力関係を壊し、それらの成分が土中に蓄積されたり川や海に流れ込んだりすることが多くの命に与える影響を考えていきましょう。
やれることはいろいろあります!
Posted by 艸木 at
09:34
│Comments(0)